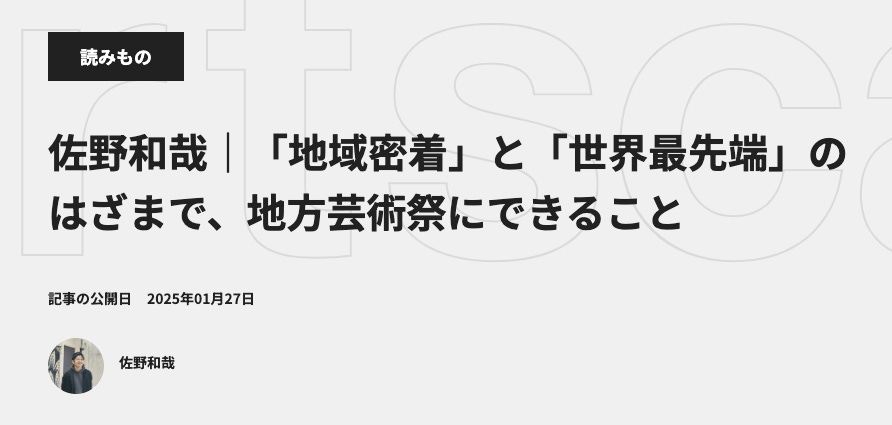#143 デザインとアート、コミュニケーション
デザイン系からアート系に移って学んだ、こちら側の原理原則
このニュースレターは基本無料でお送りしております。現在は1週間ごとに、全員閲覧可能なレターと有料会員限定のレターをお送りしています。詳しくはこちらをご覧ください。
下記にメールアドレスを入れて「Subscribe」を押し、一番右の「None」を選んで、届いたメールから確認リンクを押していただくと無料登録完了です!
今回は一部有料(SNSやめる部員向け)の回です。途中まで無料でも読めます。
お知らせ
いきなりお知らせです。
artscapeさんに記事を書かせてもらいました。それらしいタイトルで札幌国際芸術祭の宣伝をしてます。でも結構大事なこと書いてると思います。
よろしければこちらからどうぞ!:https://artscape.jp/article/29919/
あと今週から次回の札幌国際芸術祭に向けた今年のプレイベントが始まります。わたしもいろいろやってますが、特に雪まつり会場の展示”Yukikaki Research Station"にガッツリ関わってて、めちゃいい感じなので見に来てほしいです。2/7にはトークもあります。
詳細はこちらから!: https://siaf.jp/pre2025_winter/
デザインとアートのルールの違い
今年は作品の設営に関わらせてもらった。上記の通り”Yukikaki Research Station"という、SIAF2020で展示される予定だった作品。アーティストのニコラス・ロイさんとカティ・ヒッパさんとコミュニケーションしながらつくってきた。事前にいろいろ細かいやり取りをして、札幌駅に到着するところを迎えに行って、芸術祭チームのボスの家で楽しく飲み会をしたり、ホームセンターの駐車場で事故ったり(!)しながら、なんとか完成にこぎつけた。
マジ大変だったが、モノができるというのはとても楽しい。そしてそれを見に来てくれる人がいるということもとってもありがたい。200万人が来るというさっぽろ雪まつり会場で、今年はどんな反響が得られるだろうか。とっても楽しみ。
この制作を楽しくできたのは、アーティストのニコラスさんとカティさんがめちゃくちゃいい人たち、ということが大きい。陽気で前向き、アーティストインレジデンス百戦錬磨。こだわるところはこだわるけれど無理は言わず、柔軟にやりつつも自分たちのやりたいことはしっかりやり切る。単純にコミュニケーションが上手である。
自分は新卒の広告代理店から10年以上、広く見ればクリエイティブ産業の中で生きてきた。必ずそこにはつくり手がいて、場合によっては発注者がいて、その受け取り手・鑑賞者がいて、その間でさまざまな制約のもとにアウトプットをつくって世に出す、ということを繰り返してきた。そのどれもが自分にとって刺激的で、いい経験になるものだった。
でも前回のSIAF2024の準備期間からこの3年ほど、デザイン系からアート系に軸足を移して、ここはまたかなりルールが大きく違うなと感じている。
意思決定の比重
アートの仕事に携わっていて感じる、デザイン系の仕事との一番大きな違いは、成果物について制作者に委ねられている分量が圧倒的に大きい、ということである。
デザイン系の仕事は、基本的に必ずクライアントや解決したい問題があり、その思いに応えたり、問題を解決するためのアプローチが取ることが制作のゴールになる。いくらつくり手の実現したいことがあっても、お題に答えることができていなければ何の意味もなさないが、逆にお題に答えることができてさえいれば、つくり手が実現したいことをいくらでも盛り込める。それが難しくもおもしろいところ、仕事の醍醐味である。
でもアート系の仕事は、クライアントや解決したい問題よりも、アーティストが伝えたいこと・表現したいことが、いかにいい手段・いい伝え方で発露しているか、ということがゴールになる。当然大きな方向性やキュレーションは存在しているし、そこから外れているようなものはその仕事において求められることはないが、「何をテーマにしてつくるか」からアーティスト自身が(場合によってはキュレーターらとともにだが)設定する。意思決定の比重が相対的にアーティストに寄ってくる。
そうすると何が起こるかというと、まずはデザインよりも相対的に、つくり手が持つ意思決定権、つまり権力が大きくなる。それと関連して、特に芸術祭など現代美術の展覧会は、(事前に打ち合わせやプレゼンテーションなどがあるとはいえ)事前に予期できない新作が披露されることも多く、発注側が作品を細かくディレクションすることも普通はあまりないので、不確定要素が大きくなる。
そうなると、もはや制作物ではなく、人間同士のコミュニケーションでなんとかしていくしかないように思える。それはどういうことか。
作品と制作と人柄
アートは問題解決ではなく問題提起である、というような使い古されたような言い回しもあるが、最近の自分の感覚では「アートは問題解決ではなくコミュニケーションである」と言える気がしている。
たとえば問題が解決するということには、「面倒なコミュニケーションを一切不要にする」ということも往々にして含まれる。デザインは(ものによるが)コミュニケーションを少なくすることも含めて快適にすること、アートは作品を通してコミュニケーションを不快にすることも含めて活性化させるもの、とも言えるだろう。
デザインはデザインそれ自体がメッセージになることは基本的にはない。例えば道路標識や建物の案内は、ただのルールや指示、位置や感覚の表示であり、なんらか個人や団体のメッセージを直接的に持つわけではない。しかしアート作品をつくっている人は、みんな何かのメッセージを伝えたくて作品をつくっているはずである。というか、自覚的であろうとなかろうと、作品は「メッセージを伝えない」ということも含めてメッセージになってしまう。
そうすると、デザインのように直接的な問題解決の目的やディレクション、コントロールなしに、アートのアウトプットのクオリティや方向性を揃えるためには、もう率直にコミュニケーションするということしか基本的にはない。
1年ほど前の記事になるが、1年前のSIAF2024の真っ最中、